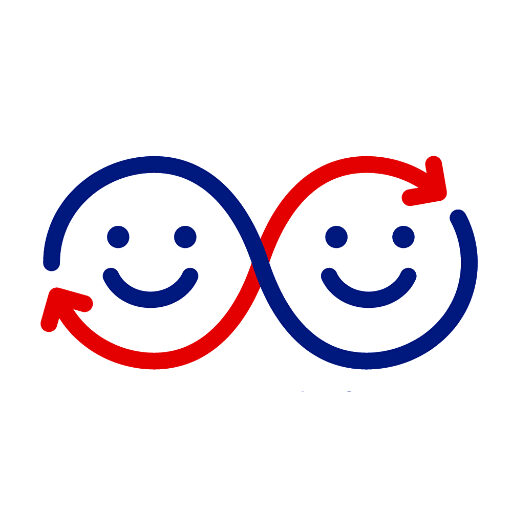7月に厚生労働省が最新(2021年)の子どもの貧困率を、11.5%と公表しました。
割合にすると8.7人に1人。
子どもの貧困が注目されたはじめた当時は6人に1人(16.3%)と言われていたので、だいぶ改善されてきた印象を受けます。
では、どのような背景があって数値的に改善しているのか。
そもそも、子どもの貧困は改善していると言えるのか。
そのことを考えるにあたって非常に参考になるのが、8月14日に三菱UFJリサーチ&コンサルティングが発表した「子どもの貧困率はなぜ下がっているのか? -統計的要因分析-」というレポートです。

このレポートは子どもの貧困率が改善している背景がコンパクトにわかりやすくまとめられているので、ぜひ目を通していただきたいです。
ここではそのポイントだけ抽出します。
- 2018年から2021年にかけて貧困率が低下しているのは、主に大人が二人以上いる世帯の貧困率が改善しているため。
- 人手不足を背景にして、共働き世帯が増え、そのほとんどが正規雇用として就労していることが影響している。
- 就労による収入増加が貧困率の低下に寄与している一方で、新型コロナ対策等の給付金を含めた社会保障は、その改善にあまり影響していない。
- ひとり親家庭でも就労による所得は増えているが、等価可処分所得80万円以下の最貧困層のひとり親家庭も増えている。
ここからは考察になりますが、社会全体が深刻な人手不足になっている流れに乗って、働いて貧困から抜け出せる家庭が増えている一方で、それができない(就労自立をしにくい)ひとり親家庭が置き去りにされている状況が見えてきます。
おそらくそういった家庭の中には、精神疾患などがあって働きにくいひとり親、子どもが不登校やひきこもりなどで働く時間を確保しにくいひとり親などが含まているものと推測します。
それにもかかわらず、目先の貧困率の低下や、就労自立を果たしている家庭が増えている状況ばかりに目を奪われてしまうと、就労自立をしにくい家庭、社会保障で支えなければならない家庭を置き去りにしてしまう危険性があると感じます。
また、可処分所得によって算出する貧困率には、インフレによる支出増の影響は表れませんし、本レポートにもあるように経済的要因にとどまらない教育格差や自殺、ヤングケアラーなどの生きづらさを抱えている子どもたちが増えている現状に目を向けなければなりません。
そもそも、ウェブで確認する限り今回公表されたデータを取り上げるマスメディアはあまり多くなく、その内容以前に子どもの貧困に対する社会的な関心が薄れてきているのではないかという懸念が払しょくできませんが、貧困率というわかりやすい数字だけで現状を見るのではなく、このレポートがあぶりだしているようなより深刻な現状に目を向けていく必要があると思います。